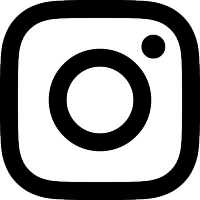新たな年を迎え

令和6年 新たな年を迎えました。
日頃から活動に対してのご理解ご協力、心より感謝申し上げます。
東京では穏やかな気候の中での元日となりしたが、北陸地方では能登半島地震が発生し、多くの尊い命が奪われ、また多くの方が被害に遭われております。
衷心よりご冥福とお見舞いを申し上げます。
救命、救助、支援活動、被災者の気持ちに寄り添いながら引き続き迅速な対応を進めなければなしません。
区議会といたしましても、何ができるか支援の方策を協議し取り組みを進めてまいります。
i改めていつ起きてもおかしくない自然災害に対する日頃の防災、減災の取り組みと防災意識の啓発、その重要性と大切さを痛感させられました。
さて、新年を迎え区政においてはいよいよ来年度の予算編成に対する本格的な議論がスタートをいたします。
様々な課題が山積する中で、不安定な世界情勢や賃金アップが追い付かない物価の高騰、エネルギー費ガソリン代の値上がり等、私たちの生活の影響を及ぼしかねい課題の発生も懸念されております。
その様な中、行財政改革の徹底とDXによる行政業務の効率化、デジタルを活用した区民サービスの充実と効率化をはじめ、あらゆる知恵を出しながら財源の確保を行い、区民の皆様の安心安全な暮らしにつながる施策の充実を行っていかなければなりません。
変化の激しい状況の中でも、誰もが安心して住み続けられる世田谷区政をこれからも実現してまいります。
その為にも、来年度の予算につきましては、多くの区民の皆様の意に副った予算としていかなければなりません。
日頃の暮らしの中で、それぞれ区政に対するご意見、ご要望、考え方等お有りのことと思います。
その貴重なご意見、考え方をいかに予算に反映できるかがこれから行われる議論に対しての大切な視点になってまいります。
皆様の貴重な声とともに、予算に対する議論をしっかりと深めまいります。
どうかご理解をいただき、これからもご示唆ご教授賜りますことお願いいたします。
どうぞご健康にご留意をしていただき、辰年のごとく上昇し幸多き年となりますことをお祈り申し上げます。
何卒本年もよろしくお願い申し上げます。
令和5年4月23日執行 世田谷区議会議員選挙
令和5年4月23日執行 世田谷区議会議員選挙 本当に厳しい戦いでしたが皆さまのお力添えにより当選することができました。
4301票、前回よりも得票数も増やしていただき心から感謝申し上げます。
4年間しっかりとお訴えした政策の実行と、地域の声を区政にお力添えに応えるべく邁進してまいります。
どうもありがとうございました。


令和5年4月23日執行世田谷区議会議員選挙報告会